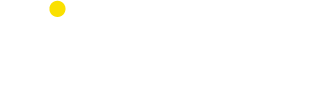2010年、せんだい演劇工房10-BOXを拠点に設立。2014年には野々下孝が宮城県芸術選奨新人賞を受賞。様々なテクストと、俳優たちが創りあげたシーンを、抽象的な関連性によって連鎖させ、ある印象を作りだすスタイルは、【演劇の暴走】と称される。常に【演劇とはなにか?】を突き付けながら、美しさと暴力性を兼ね備えた作品によって、演劇の未来を切り開き続けている。
2010年、せんだい演劇工房10-BOXを拠点に設立。2014年には野々下孝が宮城県芸術選奨新人賞を受賞。様々なテクストと、俳優たちが創りあげたシーンを、抽象的な関連性によって連鎖させ、ある印象を作りだすスタイルは、【演劇の暴走】と称される。常に【演劇とはなにか?】を突き付けながら、美しさと暴力性を兼ね備えた作品によって、演劇の未来を切り開き続けている。

溶け合う世界
仙台シアターラボ
(0)

Fukushima Meets...
仙台シアターラボ
(0)

LIVEももたろう
仙台シアターラボ
(0)

ペスト
仙台シアターラボ
(0)

透明な旗
仙台シアターラボ
(0)

幸福の果て
仙台シアターラボ
(0)

仙台シアターラボ
アート
「世界に遍在する一つの霊魂、それがわたしだ」
娘の母はヒステリックで、
男の兄は海に身投げし、
女の子どもは生まれなかった。
人生の断片が繋がった、境界のない溶け合う世界。
「あなたの中には、私の母も、あの人の兄も、この人の生まれなかった子どもも、存在しているのです」
アントン・チェーホフの名作戯曲「かもめ」を題材に、現代演劇の旗手が、新たに提唱する演劇の新形式。
野々下孝/戸田悠景/丹野貴斗/宮本一輝/渋谷颯飛(劇団かげろう)/若生彩子(ナターシャ・プレシコフ)
構成・演出:野々下孝/照明:山澤和幸/音響:本儀拓(キーウィサウンドワークス)/音響操作:島田裕充(Studio-SOLA)/舞台監督:宮本一輝/宣伝美術:岸本昌也/撮影:渡邉悠生/受付:前田成貴・鈴木大典・大村もも香/主催・製作:仙台シアターラボ

仙台シアターラボ
アート
大学の生物学研究室では、奥寺教授と大学院生たちによって、人間を作るプロジェクトが進行している。しかし、相羽良樹は自分の研究の進行が思わしくなく、野島遥は、恋人の栗山志歩が体調を崩し、実験の時間が取れなくなっている。未来を設計しながら、生活していくには、時間が足りない。ましてや死んだものや目に見えないものと過ごす時間など取れない。個人主義が進んでいる現代で、百年後の未来に寄り添う人々の物語。
野々下孝/渡邉悠生/宮本一輝/大村もも香/松本美咲/犬飼和
照明:山澤和幸/音響:山口裕次/宣伝美術:三月文庫/映像撮影: (有)スカイモーションピクチャーズ/受付:前田成貴・丹野貴斗・鈴木大典/制作:宮本一輝

仙台シアターラボ
アート

仙台シアターラボ
■テーマ「記憶のプール」
演劇を創る過程で、我々の頭の中には、先人の様々な営みや想いが浮かんでは消えていく。
アートというものはそうして誰かから受け継いで創られていくものなのかもしれない。
だとすればアートとは自己表現でありながらも、その範疇に留まらないものになる可能性を秘めている。
我々の内部に「記憶のプール」と呼べる、歴史や想いが集積したタンクの様なものが眠っていると仮定する。
演劇における故郷喪失者である我々にも「記憶のプール」はある。
古典を失い、規範を失い、続けること自体が孕んでいる絶対の孤独と戦いながら、個人の原風景をもとに演劇活動を続けている我々にも、そのプールに浮かぶことはできるのだ。
歴史はいつも否応なく伝統を壊すように動く。
個人は常に否応なく伝統の本当の発見に近づくように成熟する。
過去と未来が非連続となり、歴史感覚が失われている現在、
故郷喪失者たちは、抽象的な観念の美に酔うことしかできない。
野々下孝/澤野正樹/本田椋/飯沼由和
構成・演出:野々下孝
照明:山澤和幸/音響:中村大地/舞台監督:鈴木拓(boxes Inc.)/宣伝美術:川村智美 /情宣写真:佐々木隆二/制作協力:佐々木一美/製作:仙台シアターラボ

仙台シアターラボ
構成・演出
今回の舞台は、一九四四年にフランスで刊行された、アルベール・カミュの戯曲「カリギュラ」をモチーフにしている。
暴君として知られる、ローマ帝国第三代皇帝カリギュラを題材に書かれた戯曲である。
「カリギュラ」の登場人物たちは皆恐ろしい程の情熱で幸福へと向かう。
困難を見付けだす努力こそが才能であり、才能のある者だけが見ることができる最果てに、彼等は向かう。
「幸福の果てには、苦しみの国があり、苦しみの果てには、不毛のすばらしい幸福がある。」
そんな、意味は通らないが、感覚的に分かるイメージを「カリギュラ」は孕んでいる。
戯曲に書かれたことは、その時点で全て死んでいる。ゆえに時代や言葉の壁を越えることはできない。
しかし「カリギュラ」が孕むイメージは、現在も生々しく脈打ち、今、日本に住んでいる我々がイメージするものと繋がっているのだ。
「カリギュラ」が孕むイメージを我々が孕み直し、
カミュが生んだ「カリギュラ」を我々が生み直す。
1944年にフランスの作家カミュが書いた作品を、2014年に日本で上演するということはそういうことだ。
我々は信じている、
イメージが、時代も国境も超えて観客に着床することを。
そしてそのときこそ、作品が普遍性を獲得することを。
それができる演劇が現代劇なのだと。
野々下孝/本田椋/飯沼由和/豊島豪
照明:山澤和幸/音響:藤田翔(キーウィサウンドワークス)/舞台監督・舞台美術:澤野正樹/テクニカルアドバイザー:鈴木拓(boxes Inc.)/宣伝美術:川村智美/情宣写真:佐々木隆二/制作協力:佐々木一美/製作:仙台シアターラボ

人形
仙台シアターラボ

溶け合う世界
仙台シアターラボ

販売中
仙台シアターラボ
ドラマ アート ダンス・舞踏・パフォーマンス
ここは人形化された人柱たちの墓場であり、地球への来訪者の追憶の世界。
ヘルメルと息子のトムは理想と現実の間でしばしば対立する。
ヘルメルは娘のローラを専門学校に通わせるが、ローラの内気な性格のためうまく行かない。
妻のノーラは今までにヘルメルから愛情を受けていると思っていたが、実は自分を人形のように可愛がっていただけであり、一人の人間として対等に見られていないことに気づき、ヘルメルの制止を振り切って家を出る。
野々下孝/宮本一輝/丹野貴斗/戸田悠景/高野太地/高橋ナオミ/のぐちひなの/石岡ちひろ/塚本翔太
原作:テネシー・ウィリアムズ作「ガラスの動物園」,ヘンリック・イプセン作「人形の家」/構成・演出:野々下孝
照明:山澤和幸/音響:本儀拓(キーウィサウンドワークス)/選曲・衣装・制作:野々下孝/舞台監督:宮本一輝/舞台美術:野々下孝・丹野貴斗・塚本翔太/劇中歌作成・映像:戸田悠景/宣伝美術:岸本昌也/撮影:渡邉悠生/受付:前田成貴・鈴木大典・大村もも香

販売終了
仙台シアターラボ
アート
「世界に遍在する一つの霊魂、それがわたしだ」
娘の母はヒステリックで、
男の兄は海に身投げし、
女の子どもは生まれなかった。
人生の断片が繋がった、境界のない溶け合う世界。
「あなたの中には、私の母も、あの人の兄も、この人の生まれなかった子どもも、存在しているのです」
アントン・チェーホフの名作戯曲「かもめ」を題材に、現代演劇の旗手が、新たに提唱する演劇の新形式。
野々下孝/戸田悠景/丹野貴斗/宮本一輝/渋谷颯飛(劇団かげろう)/若生彩子(ナターシャ・プレシコフ)
構成・演出:野々下孝/照明:山澤和幸/音響:本儀拓(キーウィサウンドワークス) /音響操作:島田裕充(Studio-SOLA)/舞台監督:宮本一輝/宣伝美術:岸本昌也/撮影:渡邉悠生/受付:前田成貴・鈴木大典・大村もも香/主催・製作:仙台シアターラボ
![]() JASRAC許諾番号:
JASRAC許諾番号:
9015824001Y43136
![]() NexTone許諾番号:
NexTone許諾番号:
ID000002082